持病がある場合の生命保険の入り方
持病があると生命保険に入りにくい

持病があり通院・投薬などの治療を受けている方の中には、生命保険への加入が難しいと考えている方は、決して少なくありません。
一般に生命保険は、加入者の身に起きる万一の事態(死亡や入院)を費用面でカバーするために加入するものです。しかし、過去の入院歴や、現在治療中の持病によっては、健康な人と比較するとリスクが著しく高いと判断され、結果的に保険に加入することが難しくなってしまいます。
持病があっても入れる保険は保険料が高い?
その一方で、一部の生命保険は、持病があっても加入できるよう設計されています。たとえば、通常よりも告知項目が少ない「引受基準緩和型(限定告知型)」の生命保険や、告知不要で加入できる「無選択型」の生命保険。これらの保険は、契約時の告知項目を減らす、あるいはなくすことで、持病がある人でも生命保険に加入できるよう設計されています。
ただし、幅広い健康状態の人に対応する生命保険は、そのぶん保険料が高くなるというデメリットもあります。引受基準緩和型や無選択型の保険料は、一般的な生命保険と比較すると2割から5割程度アップ。商品によっては2倍以上になるケースもあります。
本来であれば、加入者を費用面でサポートするための生命保険が、割高な保険料のために家計の負担となっては本末転倒です。
そこで今回は、持病のある人が生命保険に加入する際の保険商品の選び方、告知のポイントを解説します。
保険料で損しないための生命保険の入り方
≪ 生命保険の入りやすさ ≫
| 一般的な生命保険 | 引受基準緩和型 | 無選択型 | |
|---|---|---|---|
| 告知事項 | 多め |
少なめ |
なし |
| 入りやすさ | 通常 |
やや入りやすい |
誰でも入れる |
| 保険料 | 割安 |
~ やや高め |
割高 |
| 保障範囲 | 広い |
~ やや限定される |
限定される |
上記の表からもわかるように、持病があっても入れる生命保険の多くは、保険料が割高になるだけではなく、保障範囲が狭まる等、何らかの条件が加わります。そのため、まずは保険料がもっとも安く、保障範囲も広い一般的な生命保険を第一候補とし、次に引受基準緩和型、最後に無選択型保険という順序で検討を進めていくと良いでしょう。
≪ 持病がある場合の生命保険の検討順序 ≫
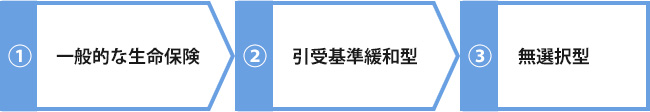
まずは一般的な生命保険を検討しよう
持病がある場合でも、まずは一般的な生命保険からトライするのがおすすめです。疾病の引受基準は保険会社によって異なり、病名や現在の健康状態によっては加入可能な生命保険が多くあります。1社目で断られたとしても、別の保険会社であれば審査が通るというケースも決して珍しくありません。
生命保険の審査が通りやすくなる告知のポイント
一般的な生命保険の審査でもっとも重要となるのは、正確な告知です。服用している薬品名や、検査数値、手術の術式名などは、処方記録(お薬手帳など)や通院時の記録をもとに正確に記載しましょう。
また、数値の変化や病気の経過などが以前と比較して改善しているようであれば、その旨を申告することも大切です。
なお、医師の診断書や健康診断結果は、不要で加入できる生命保険も増えていますが、持病がある方の場合、あえてこれらの資料を添付することで審査に有利に働く場合もあります。
引受基準緩和型は終身タイプと定期タイプを使い分け
一般的な生命保険への加入が難しい場合に選択肢となるのが引受基準緩和型保険です。加入時の告知は2~5項目程度と一般的な生命保険と比較すると少なめ。保険料は一般の生命保険と無選択型保険の中間程度です。
ただし、一般的な生命保険とは異なり、加入から1年以内は保障額が半分になる場合があるなど保障内容に制限が設けられている点には注意が必要です。
※不慮の事故やケガが原因の死亡(災害死亡)は、加入期間に関わらず全額保障されるケースが多い。
引受基準緩和型の生命保険を検討する場合は、保障の必要な期間やご自身の病状に応じて、終身タイプと定期タイプのどちらを選択するかを決めると良いでしょう。
たとえば、「子供が独立するまで」や「定年を迎えるまで」等、一定期間のみ手厚い死亡保障が欲しいという場合であれば、終身タイプよりも定期タイプの保険を選択したほうが保険料を抑えることができます。
一方、葬儀代のように死亡時にかかる諸費用を準備したい場合は、終身タイプの引受基準緩和型保険がおすすめです。
≪ おすすめの引受基準緩和型生命保険 ≫

| 特徴 | 引受基準緩和型保険としては業界初となる定期タイプの死亡保険。終身タイプの引受基準緩和型保険と比較して大幅に割安な保険料を実現。 |
|---|---|
| 主契約 | 死亡保障 ※高度障害保障はなし |
| 死亡保険金・災害死亡保険金 | 200万円から2,000万円まで |
| 保障期間 | 10年間、55歳満了、60歳満了、65歳満了、70歳満了 ※加入年齢により選択可能な保障期間が異なる |
| 支払削減期間 | 契約日からその日を含めて1年以内に死亡保険金の支払事由に該当した場合、支払われる死亡保険金額は、基本保険金額の50%に削減 ※災害死亡時は減額なし |
| 保険料* | 55歳…月額6,849円 |
* 試算条件…男性、70歳満了、死亡保険金:300万円、災害保険金:300万円
こちらもチェック!

引受基準緩和型死亡保険
持病があっても入りやすい死亡保険を比較。各社の保険料・保障内容・評判は?
無選択型は保険料と保障内容のバランスを重視
引受基準緩和型保険への加入も難しい場合は、告知が不要な無選択型を検討しましょう。ただし、無選択型保険は保険料が割高なうえ、加入から2年間は死亡保険金が支払われない(万一の際は既払込保険料相当額が還付される)というデメリットもあります。
そのため、無選択型の生命保険を検討する場合は、保険料と保障内容のバランスを重視すると良いでしょう。
たとえば、希望している死亡保障額を準備するためには、毎月の保険料がいくらになるのか、その死亡保障額を準備する方法は保険しかないのか(現在保有している貯蓄や不動産などの資産で賄うことができないか)等を考えてみることも大切です。
まとめ

「持病がある場合の生命保険の入り方」いかがでしたでしょうか。
持病のために生命保険に入りにくいと感じている方でも、病状を正確に告知したり引受基準の緩やかな保険商品を選んで死亡保障を準備することは充分可能です。
ただし、持病があるケースでは、保険料が割高になるなど、どうしても保険のコストパフォーマンスは低下しがち。
病状や検査数値などが正常に近づいてきた場合は、保険を見直す等、割高な保険料を払い続けないようにする工夫も大切です。
ご自身の健康に不安がある方は、持病があっても入れる生命保険のメリットを最大限に生かしつつ、自分自身の身体と毎月の保険料にも気を配った保障プランを考えていくようにしましょう。